米国株に投資する選択肢の一つとして、ETFの購入があります。
今回は米国ETFの中から厳選したオススメの銘柄を10個紹介していきます。
米国ETFに興味のある方はぜひ参考にしてみてください。ネット証券でも簡単に購入することができます。ぜひこの記事を最後まで読んでいただいて、行動に移していただけたら幸いです。
ETFとは?
オススメの米国ETFを紹介する前に、簡単にETFとは何かを説明しておきます。(必要ないよという方は飛ばしてもらって大丈夫です)
ETFとはいわゆるファンドのことを指します。例えば、日経平均株価に連動するファンドを購入することは、日経平均株価を構成する255社を丸ごと買うようなものです。
ファンドには、少ないお金でたくさんの企業に投資できるというメリットがあります。

「ファンドとは”お弁当パック”だ」とイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません。
日経平均株価の連動ファンドを購入すること=日本企業詰合せパックを購入すること
このイメージを持ってもらえれば大丈夫です。つまりS&P500連動ファンドを買うのは、アメリカ弁当を買うことと一緒ということです。(おかずを1つずつ買い集めなくてもお弁当を買うと効率が良いのと同じ)
そしてファンドには大きく2種類があります↓
- ETF
→株式同様にリアルタイムで取引が可能 - 投資信託
→リアルタイムで取引ができない
大きな違いはそこまでありませんが、リアルタイムで取引が可能かどうかが違いの一つになり、今回は機動的な方の「ETF」のファンドを紹介していきます。
ETFはとても便利です。
- 少額から投資が可能
- 多くの銘柄に分散投資ができる
- プロが資産を管理してくれる
ETFは便利な一方で、こういった便利なものには”コスト”がかかります。
ETFを購入する際には「買付手数料」なるものがかかります。単体で見れば投資額の0.5%ほどであったりしますが、投資額が大きくなればなるほどその金額も大きくなってしまいます。
長期にわたって投資を継続する人や、売買を繰り返す人にとって「手数料」は見てみぬふりができない存在です。
資産運用の鉄則は、
- ムダなコストは極限まで抑える
ことであり、買付手数料無料のメリットは大きいです。この買付手数料を極限まで抑えた銘柄を紹介していきます。
これから米国ETFを紹介していきますが、その前に前提として以下のことをお伝えします。
これから紹介する銘柄は、投資が趣味ではない”普通の人”にとってプラスアルファ部分の投資であって、「全財産、これに投資しろ!」といったものではありません。
あくまでもコア部分を強化するサテライト部分の紹介になります。ご承知おきを。
おすすめの米国ETF10選
お待たせしました。それではおすすめの米国ETFを10個紹介していきます。
※トレーディングビューのサイト上のデータを参照しております(2025.3.23時点)
VT(全世界株ファンド)
トップバッターは、VT。全世界株ファンドです。
投資対象は、先進国・新興国の株式。銘柄数は9,563。分配金利回り1.92%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

資本主義経済が今後も続くならという前提で、100年でも200年でも保有できる優良ファンドです。
VTが消滅するときには、人類滅亡の危機に陥っているといっても過言ではない、超優良ファンドの一つと言えます。
VTI(全米株ファンド)
2つ目は、VTI。全米株ファンドです。
投資対象は米国全体(上場している小型株から大型株全部)。銘柄数は3,540。分配金利回りは1.32%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

資本主義、民主主義を愛してやまない人にはマストの銘柄と言えるでしょう。アメリカ万歳。
VOO(S&P500連動ファンド)
3つ目は、VOO。最強株価指数であるS&P500に連動する米国株ファンドです。
投資対象は米国の大型株(S&P500採用企業)。銘柄数は504。分配金利回りは1.29%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏はこう言います。
「妻に残す遺産の9割をS&P500のインデックスファンドで運用する。」
伝統と信頼のS&P500。これに投資できるETF、それがVOOです。
EPI(インド株ファンド)
4つ目は、EPI。インドで利益を出している企業に投資するインド株ファンドです。
投資対象はインド株(上場している小型株から大型株)。銘柄数は414。分配金利回りは0.28%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

コア銘柄を米国株や先進国株にした人が、サテライトとして新興国のうちの有望国に投資したい。こういった時に検討するタイプのファンドと言えるでしょう。
GLDM(金ETF)
5つ目は、GLDM。ゴールドの価格に連動する金のETFです。
投資対象はゴールド。銘柄数は1。分配金利回りはありません(ゴールドの為)。
誕生(2018年)から現在までのチャートはご覧の通り↓

GLDMは配当金はないので価格変動が成績の全てになります。よって、株式のように成長性に期待するのではなく、分散投資の一角としての守りの役割と言えます。
ゴールドに投資する場合、ふたつの選択肢があります。
- 現物
→購入時に消費税がかかる
→売買手数料が高い
→保管コストも高い - ETF
→売買手数料が安い
→保管コストもかからない
上記のことから、一般論としてはETFがオススメとなります。
GLDMは金ETFの中で現状最も経費が安く、最有力候補の銘柄になります。
QQQ(ナスダック上場株ファンド)
6つ目は、QQQ。ナスダック上場株ファンドです。
茄子とアヒルの組み合わせパックのことではありません()
ナスダックとは世界最大規模の新興企業向け株式市場のことを言います。この市場に上場している企業はITやハイテク企業が多いです。
投資対象はナスダック上場の非金融企業の時価総額TOP100社の株式。銘柄数は102。配当利回りは0.59%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

米国の新興市場に投資をするだけあって、高い成長を見込めます。今後も高い成長性を期待できることでしょう。サテライトとして米国のハイテクセクターに賭けるのなら、QQQは有力候補の一つになります。
SPYD(米国高配当株ファンド)
7つ目は、SPYD。米国の高配当株ファンドです。
投資対象はS&P500の中で最も利回りの高い企業約80社。銘柄数は80。分配金利回りは4.34%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

利回りが結構高いです。高配当株を求める方にとっては、選択肢の一つとなることでしょう。
ただし、高配当株ファンドの中でも「利回りが高い分、リスクも大きい」ファンドがSPYDです。ポートフォリオの利回りを高めるためのスパイスとしての活用がおすすめと言えるでしょう。
AGG(米国債券ファンド)
8つ目は、AGG。米国債券ファンドです。
これ一本で、米国の優良な債券に幅広く投資することができます。
投資対象は米国投資適格債券。銘柄数は12,140。分配金利回りは3.72%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

債券は元々「利息で手堅く稼ぐ」ものです。値上がりでのリターンはそこまで大きくないのが通常です。ここ数年でリターンを大きく減らしている要因として、金利の上昇が挙げられます。
債券価格と金利はシーソーの関係にあります。金利が上がると債券価格は下がります。一方金利が下がると債券価格は上がります。
今日、利上げが話題となっています。利上げをするということは、金利が上がるので債券価格は下がります。そういう意味では、今AGGに投資をするのが時期が悪いといえるかもしれません。
「金利を下げる」という発言が出始めたときに、購入の検討余地があるでしょう。
VGT(米国テクノロジー株ファンド)
9つ目は、VGT。米国のテクノロジー株ファンドです。
「情報技術関連の会社の株を集中的に購入したい!」という人の為のファンドです。
投資対象は、米国の情報技術セクターの大型株・中型株・小型株。銘柄数は314。分配金利回りは0.66%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

ここ数年での成長率にはすさまじいものがあり、宝くじのようなロマンがある銘柄です。言葉の通りVGTには人生を変えるパワーがあります。
ですがこの成長が今後10年続けば夢のようですが、果たして結果はどうなるでしょう。高い成長性を誇る業界だというのには変わらないですが、このペースで伸び続けるかどうかは誰にもわかりません。
IYR(米国不動産株ファンド)
最後は、IYR。米国の不動産株ファンドです。
投資対象は、米国の不動産セクターの株式。銘柄数は67。分配金利回りは2.56%。
チャートはご覧の通り(10年間)↓

株式や債券が伝統的な資産と言われる一方で、ゴールドや不動産などは代替的な資産(オルタナティブ)と言われます。
分散投資の一角としてポートフォリオに多様性を持たせるのならIYRのような不動産セクターの株式がその選択肢の1つになるでしょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。今回は、米国ETFおすすめ10選を紹介してきました。参考になるところがありましたら幸いです。
最後に10選全てをざっくりと並べておきます。
- VT(全世界株ファンド)
- VYI(全米株ファンド)
- VOO(S&P500連動ファンド)
- EPI(インド株ファンド)
- GLDM(金ETF)
- QQQ(ナスダック上場株ファンド)
- SPYD(米国高配当株ファンド)
- AGG(米国債券ファンド)
- VGT(米国テクノロジー株ファンド)
- IYR(米国不動産株ファンド)
今回は「お金の大学」でおなじみ両学長さんの動画をもとに作成させていただきましたが、私自身も紹介した銘柄のいくつかを少数ですが保有しております。記事内でも少し触れましたが今回紹介した銘柄はあくまでもサテライト要因です。まずはつみたてNISAやiDeCoなどで固い銘柄(全世界もしくはS&P500)を購入したうえで、分散の意味合いで買ってみるのがおすすめです。
ネット証券でぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか?

ちょっと投資が面白くなってきて、何か買いたいかもと思っている人にはよさそう。
アメリカ最強時代がいつまで続くかわかりませんが、”買っておけばよかった”と思いそうなら”買っておけばいい”ものなんだなぁ。かねお。
ではまた。
参考にさせていただいた動画↓

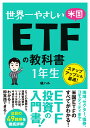

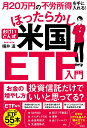

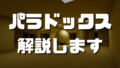
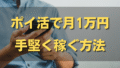
コメント