今年も読んだ本を全部紹介する記事を立ち上げます。
私が実際に読んだ本の、「概要」「印象に残った部分」「感想」を共有していきます。
それではさっそくいきましょう。
- 2023年読んだ本
- 習慣を変えれば人生が変わる/マーク・レクラウ
- シン・サラリーマン/サラタメ
- 思考力の地図/細谷功
- 働き方5.0/落合陽一
- イェール大学人気講義 天才~その「隠れた習慣」を解き明かす/クレイグ・ライト
- 実践型クリティカルシンキング/佐々木裕子
- 半分、減らす/川野泰周
- 22世紀の民主主義/成田悠輔
- お金持ちになれる黄金の羽根の羽根の拾い方/橘玲
- 運転者/喜多川泰
- 働き方2.0vs4.0/橘玲
- ノックの音が/星新一
- 進化論マーケティング/鈴木祐
- デイトレード/オリバー・ベレス
- CHANCE/犬飼ターボ
- 東京貧困女子。/中村淳彦
- 電柱鳥類学 スズメはどこに止まってる?/三上修
- たった一通の手紙が、人生を変える/水野敬也
- 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書/藤尾秀昭
- 大谷翔平120の思考/大谷翔平
- 人望が集まる人の考え方/レス・ギブリン
- 「やりたいことの見つけ方」がすごい!/リチャード・プロディ
- 賢者の睡眠/メンタリストDaiGo
- あした死ぬかもよ?/ひすいこたろう
- 13階段/高野和明
- 喜ばれる人になりなさい/永松茂久
- 天才IT大臣オードリー・タンが初めて明かす問題解決の4ステップと15キーワード/オードリー・タン
- 世界史を大きく動かした植物
- 僕が親ならこう育てるね/ひろゆき
- 最高の体調/鈴木祐
- 面白くて眠れなくなる植物学/稲垣栄洋
- 人工知能は人間を超えるか/松尾豊
- 朝1分間、30の習慣。/マツダミヒロ
- すぐやる人は、うまくいく/中谷彰宏
- まとめ
2023年読んだ本
2023年読んだ本を随時更新していきます。
気になる本がありましたら、リンクも張っておきますのでそこからチェックしてみてください。
習慣を変えれば人生が変わる/マーク・レクラウ
私たちの心は非常に強い力を持っている。まさに古来の金言にあるとおり、人間は心の中で思っているとおりの人物になるのだ――。アメリカ・ドイツ・イギリス…各国で続々ベストセラー入り!あなたの人生の転機になる、とても簡単で、どれも大切なこと。いますぐに実行できる、100の人生のコツ
ひとこと感想
習慣にすれば人生が変わるという100の習慣を一挙にして読むことができる一冊です。「確かにこれをやれば人生が変わりそうだな」という内容が多々ありました。著名人の名言なんかも紹介されていて面白かったです。
印象に残った部分
心配事の54%はたぶん現実にはならないことだった。26%が変えることのできない自分の過去の行為に関するものだった。10%が他人の意見に関するものだった。4%がすでに解決した個人的な健康問題だった。注目する必要があったのは、わずか6%だった。
※本書より引用
シン・サラリーマン/サラタメ
人生100年時代が到来。「安定」の意味が180度変わった。「大企業での出世」が安定を意味しなくなった今、あなたに真の安定をもたらすのは、「3つの武器」を持つこと。[1]リーマン力 [2]副業力 [3]マネー力これら3つの武器を持つシン・サラリーマンになることだ。
ひとこと感想
書籍解説系YouTuberサラタメさんが書いた本で、分厚い本ですがとても読みやすい構成でサクサクと読むことができました。まるで「嫌われる勇気」のような対話形式の一冊なのでとてもとっつきやすいかなと思います。リーマン力を高めるというフェーズが特に面白く参考になりました。
印象に残った部分
報連相で「事実」と「意見」は別物。「事実」が土台となる。良く見せようとすると、「意見」が多くなるので注意。まず「事実」を伝える。「意見」を伝える時は、注釈を入れてから。最後に、「事実」と「意見」を基にした「行動」まで伝えられるとベスト。
※本書より引用
思考力の地図/細谷功
知識とは過去に(自分自身を含む)「誰かがやったこと」や誰かがまとめて形に残したものであり、「過去の集大成」といえます。これに対して思考力は、新しいものや自分なりのもの、つまり「違うもの」を生み出すための能力であり、変化が激しい時に特に重要になるのです。
ひとこと感想
とても読みやすい本だったなというのがまずの感想でした。思考力の大切さを深堀して離されていてタメになる箇所がたくさんあって面白かったです。
印象に残った部分
「別の世界でこうだったから、この世界でも同様の結果が得られるのではないか」と考えるのは、科学の世界でもよく用いられます。そのようなことで、新しい結論を出すときに仮説を持ってくるネタを「遠くから借りてくる」のがアナロジーです。
※本書より引用
働き方5.0/落合陽一
「社会の前提」は、すべて変わった。「コロナ」によって、社会の前提がすべて変わった。2020年、我々の「働き方」は大変革を迫られた。リモートワークによって使える人的・時間的リソースが限られる中で、「やるべき仕事」が自ずと抽出されてきた。無駄な会議、出なくてもいいミーティングは排除され、ビジネスチャットやビデオ会議などテクノロジーで解決できることはそれに任せることが増えてきた。そして、「リモートワークのみで済む人材」への置き換えも始まりつつある。では、「人間がやるべき仕事とは何か」
ひとこと感想
これからの働き方がどのように変化していくかがジャンルごとに書かれていて面白く読めました。著者ならではの視点からの考え方を学ぶことができる一冊です。
印象に残った部分
就活性の多くが必死になって「正社員」の座を求めたり、達観して今の人生を受け入れ始めたりしているのです。その争いに屋ずれて挫折する人がたくさんいる訳ですが、これは何かがおかしいと思います。時代が変わろうとしているのに、相変わらず時間を切り売りするホワイトカラーを目指すことで、余った富を獲得するチャンスを自ら手放しているのです。
※本書より引用
イェール大学人気講義 天才~その「隠れた習慣」を解き明かす/クレイグ・ライト
「天才とは何か?」「天才に必須の資質や能力、思考や行動のパターンはあるのか?」「どんな人でも天才になれるのか?」アインシュタイン、キュリー夫人、ホーキング博士などの科学者、イーロン・マスクやスティーブ・ジョブズのような実業家、シェイクスピアやヴァージニア・ウルフなどの作家、レオナルドやゴッホ、草間彌生などの芸術家、モーツァルト、ベートーベンといった音楽家、レディ・ガガやカニエ・ウェストのような現代のアーティストから、エリザベス1世やチャーチルのような政治家まで、幅広い分野において、世界を大きく変える影響力を持った「天才」を、さまざまな観点から分析。特徴的な思考や行動パターンを明らかにしていきます。
ひとこと感想
様々な天才たちの実例紹介や、天才についての深堀をしていく一冊。天才と言っても一種類ではなく多種多様な天才がいるのだなと考えさせられました。個人的には読破するのにちょっとむずかしかったと感じた。さすがイエール()
印象に残った部分
難しいのは、隠れた天才を見つける検査方法を見つけることだ。これについてはアインシュタインの言葉としてよく言われていることが一番しっくりくるのではないだろうか。「皆、天才である。しかし、木登りの能力で魚を評価したら、魚は、自分はダメなんだと思って一生を過ごすことになるだろう」。
※本書より引用
実践型クリティカルシンキング/佐々木裕子
実践型クリティカルシンキングとは、「目指すもの」を達成するために「自分の頭」で考え、行動し、「周りを動かす」ための実践的な思考技術です。世の中の変化のスピードが速く、じっくり悩んでいる時間がない。これまでまったく経験のない、新しいことに取り組む場面が増える。グローバル化が進む中で、どんな人も巻き込める、簡潔で論理的な根拠を示す必要がある。こうした状況の中で自ら目指すものを設定し、その目標を戦略的に達成していくことができるのが
クリティカルシンキングです。
ひとこと感想
実例を用いて、その命題をどう解決していくかを考える章がとても面白かったです。思考停止で作業する時代は終わり、深くまで考えられる人種が生き残っていける世界になっていくのだなと思いました。クリティカルシンキングを身に付けていきたいです。
印象に残った部分
最初はズームインしすぎず、「他にはないのか?」とズームアウトする。最初「少子化対策」が出たらそっちにずっと行っちゃうんじゃなくて、「他にはないのかな。他にはほんとにないのかな」という風に考え続ける。すると、新しい枝を思いつくんですね。
※本書より引用
半分、減らす/川野泰周
「半分、減らす」「1/2を心がける」と、驚くほど毎日がすっきりする。ストレスも減る。生産性が上がる。まずは、身のまわりの物を片づけることから。物、消費、情報、食事、仕事、スマホ……いまより半分、減らしてみる。1/2を心がけてみる。医師で禅僧の著者が指南する、より少なく、より豊かに暮らすための「シンプル生活術」
ひとこと感想
ミニマリスト的な考えが学べる一冊でした。食べ物であった利確であったりととにかく「半分に減らすこと」でよいことがいろいろあるのだなと思いました。モノであふれかえってしまっているなと思う方におすすめの一冊です。
印象に残った部分
どんなに「買いたい衝動」が高まっても、ネット通販では注文するまでに「ひと晩寝かす」ことを心がけましょう。
※本書より引用
22世紀の民主主義/成田悠輔
断言する。若者が選挙に行って「政治参加」したくらいでは日本は何も変わらない。これは冷笑ではない。もっと大事なことに目を向けようという呼びかけだ。何がもっと大事なのか? 選挙や政治、そして民主主義というゲームのルール自体をどう作り変えるか考えることだ。ゲームのルールを変えること、つまり革命であるーー。22世紀に向けて、読むと社会の見え方が変わる唯一無二の一冊。
ひとこと感想
民主主義と選挙が主な題材の一冊で、成田さんならではの切り口から論じられていてとても面白く読めました。今の民主主義や選挙の仕組みが日本を停滞させている。だからこそそれを変えるには大きな革命が必要となるということが本書から読み取れました。
印象に残った部分
だが、ほとんどの政治家は知名度も権力も試算も中途半端なダダの人で、人から気に入られ続けなければ立場を保てない。その残念な現実がシルバー民主主義を生んでいる。ひとりひとりの政治家のビビりこそがシルバー民主主義の実態なのだろう。
※本書より引用
お金持ちになれる黄金の羽根の羽根の拾い方/橘玲
自由な人生を誰もが願う。国、会社、家族に依存せず生きるには経済的独立すなわち十分な資産が必要だ。1億円の資産保有を経済的独立とすれば欧米や日本では特別な才は要らず勤勉と倹約それに共稼ぎで目標に到達する。黄金の羽根とは制度の歪みがもたらす幸運のこと。手に入れると大きな利益を得る。誰でもできる「人生の利益の最大化」とその方法。
ひとこと感想
橘玲さんのお金の本の代表的な一冊。ロバートキヨサキさんの「金持ち父さん貧乏父さん」の内容と似たような話が多かった印象ですが、お金持ちになりたいと思う人全員が一度は読んでおきたい本かなと思いました。
印象に残った部分
「金持ちはケチだ」とよく言われますが、これは論理が逆で、「ケチだからこそ金持ちになれた」のです。確実に資産を増やす方法が目の前にあるにもかかわらずそれを実行しない人間が、資産形成に成功できるはずがありません。
※本書より引用
運転者/喜多川泰
報われない努力なんてない!累計100万部 喜多川泰、渾身の感動作!中年にして歩合制の保険営業に転職し、二年目の修一。しかし、なかなか思うように成果が上がらない日々を過ごしていた。ある日、唐突な担当顧客の大量解約を受け、いよいよ金銭的にも精神的にも窮地に追いやられてしまう…
ひとこと感想
小説の中に盛り込まれているメッセージがとても刺さる内容でした。この物語に出てくる「運転車」とは一味違った意味を持ちます。これは読んでみればわかること。考え方で今は変わる、未来は変わる。感動出来てかつ面白い一冊なのでぜひ読んでみてください。
印象に残った部分
運は「いい」か「悪い」で表現するものじゃないんですよ。「使う」「貯める」で表現するものなんです。だから先に「貯める」があって、ある程度貯まったら「使う」ができる。少し貯めてはすぐ使う人もいれば、大きく貯めてから大きく使う人もいる。そのあたりは人によって違いますけどね。どちらにしても周囲から「運がいい」と思われている人は、貯まったから使っただけです。
※本書より引用
働き方2.0vs4.0/橘玲
「未来世界」で生き延びる方法 の4つのパートで、組織や人間関係の煩わしさから離れ、「仕事の腕」を磨いて“食っていく”ヒント満載!人生100年時代、40代から生涯現役でやりたい仕事を楽しみ、社会に役立ち、年金に頼らずお金も得る「未来志向な幸福のライフスタイル」を提案する書。
ひとこと感想
生き方や働き方が今後大きく変わっていくという主張がベースの本で、とても興味深い内容でした。未来を生き抜くうえでどのようなスタンスで働いていけばよいのかを考えさせられる一冊です。
印象に残った部分
共働きの経済効果はきわめて強力です。人生100年時代の人生設計は、「長く働く、一緒に働く」以外にないのです。
※本書より引用
ノックの音が/星新一
ノックの音とともに、二日酔いの男の部屋にあらわれた見知らぬ美女。親しげにふるまう彼女の正体は? いったい、だれのところへ、どんな人が訪れてきたのか。その目的は。これから部屋の中で、どんなことがおこるのか……。サスペンス、スリラーからコメディーまで、「ノックの音」から始まる様々な事件。意外性あふれるアイデアと洒落たセンスで描く15のショートショート。
ひとこと感想
小学生のころに読み漁った星新一作品のうちの一冊。久しぶりに読んでみましたがやはり読みやすくそして面白かったです。すべての物語が「ノックの音がした。」で始まり、終わり方は安定のミステリアチックな感じ。一本一本は短くてそれでも読みごたえがある星新一作品は本当におすすめです。読書入門書としていかがでしょうか。
印象に残った部分
ノックとブザーでは、どこか感じが違う。ノックだと、良くも悪くも、人間的な何かがある。たたき方によって、訪問者の検討がつけられる。ブザーだと、電線なるものが中間にあって、人間性が薄れてしまう。
※本書より引用
進化論マーケティング/鈴木祐
ベストセラーを連発するサイエンスライターが解説する、最新研究のエビデンスに基づく、本能を撃ち抜く「進化論マーケティング」の実践書。なぜ、世界中のマーケターが「ヒトが持つ本能」に注目するのか。それは、消費者理解が人間の本能と行動の関係性を解明することだからです。
ひとこと感想
前半部分は電子書籍でもとても面白く読み進めることができました。が、後半部分は実際に本に書き込めるような感じの作りになっていて、紙の本でじっくり書き込みながら読むと費用対効果がとても高そうだなと思いました。
印象に残った部分
顧客に意見を聞いて製品をデザインするのは本当に難しい。多くの場合、人々は自分が何を欲しているのかを分かっていないからだ。
※本書より引用
デイトレード/オリバー・ベレス
特徴は、皆が本当は気付きつつも忘れてしまいがちな事を、表現を変えながら執拗に繰り返し述べている点。本書によって、迷いの罠から逃れ、より信念を持って売買できるようになります。例えば「株式を取引するのではなく、人を取引する」という教訓。多くの初心者が、一つひとつのトレードに必ず相手がいることを認識していない。株式を買うたびに、誰かがその株式を必ず売っている。株式を売るたびに、誰かがその株式を必ず買っている。問題は「どちらが、より賢いのか」という点であり、マーケットの機微を知って、賢い側に立てるように鍛えるアドバイスをする。
ひとこと感想
株の本で気になっていた一冊。前評判通り、デイトレードの手法を学べるというよりは、株式市場における心の持ち方や姿勢を学べる精神論的内容でした。大多数の勝てない投資家と肩を並べるのではなく、少数の勝つ投資家になるために、ぜひ読んでみてほしい一冊です。
印象に残った部分
最初に取り組むのは、読者の心に変革をもたらすことである。強調しておきたいのは、一つ一つのトレードには必ず相手がいるということだ。問題は「どちらか、より賢いのか」である。それが読者なのか?あるいは、トレードの相手なのか?本書の目的は、マーケットの基調を知ることによって、「賢い側」に立てるよう、読者を鍛えることである。
※本書より引用
CHANCE/犬飼ターボ
サラリーマンになるのはいやだ! と独立を志し、いろいろな事業を試みては、失敗を繰り返す泉卓也は、ある日偶然、フェラーリに乗る弓池という成功者と出会う。なぜ自分はいままでうまくいかなかったのか? どうすれば成功者の仲間入りができるのか?人生で成功するということはいったいどういうことなのか?数々の試練を乗り越えながら、弓池から多くを学び取っていった卓也が導いたその答えとは……?
ひとこと感想
自己啓発の内容の小説でした。小難しい自己啓発書を読むのが厳しいなって人には読みやすくていいかもしれません。個人的には「七つの習慣」とか「嫌われる勇気」などの方が頭に入ってきやすかったです。
印象に残った部分
”痛みを取り除くビジネス”と”快楽を与えるビジネス”がある。痛みを取り除くビジネスにどんなものがあるかというと、節約、医療、教育、宗教の4つだ。痛みを取り除くビジネスには公共でも不況でも景気に関係なく人はお金を払う。だから痛みを取り除くビジネスは不況でも儲かる。
※本書より引用
東京貧困女子。/中村淳彦
〝その日暮らしは十分できます。もっと経済的に厳しい人がいるのも十分承知はしています。けど、ずっとギリギリの生活で、なんの贅沢もしていないのに貯金すらできない。年齢ばかり重ねて、私はいったいどうなってしまうのだろうって〟
ひとこと感想
貧困にあえぐ女性たちのリアルな声がまとめられた一冊です。貧困すぎるがゆえに夜の街で働かなくてはならないという生々しい現実を本書で体感することとなります。途中で読むのを中断してしまうくらいに重々しい内容でした。これが世の中の現実なのです。読む価値あると思います。
印象に残った部分
都内で言えば、早慶上智、MARCH在学中などは当たり前で、どちらかというと真面目よりな普通の女子大生たちが性を売っている。彼女らが口をそろえて言うのは「いくら悩んでも、選択肢は風俗しかない」ということだ。
※本書より引用
電柱鳥類学 スズメはどこに止まってる?/三上修
電柱といえば鳥,電線といえば鳥.でも,そこで何をしているの?カラスは「はじっこ派」?感電しないのはなぜ?電柱や電線の鳥に注目したら見えてきた、その知られざる生態,電柱・電線の意外な姿,電力会社と鳥たちの終わりなき知恵比べ、あなたの街にもきっとある,鳥と電柱,そして人のささやかなつながりを,第一人者が描き出す。
ひとこと感想
電柱と鳥類の関係性が超絶真面目に書かれていてとても面白かったです。なぜ電柱にとりは止まるのか?どの種類の鳥が電柱に止まりやすいのか?そんな疑問を学問していくことができます。本書にも書かれていますが、長い歴史の中で電柱に鳥が止まっているのを見られるのはわずかな時間になりそうです。その時間を大切にしていきたいものですね。
印象に残った部分
現代の鳥たちは、人間が150年かそこら前に作り出した構造物を、普段使いの足場としているのです。我々は、電柱・電線と鳥が一緒にいるという貴重な時間を生きているということになるのです。
※本書より引用
たった一通の手紙が、人生を変える/水野敬也
ベストセラー作家、水野敬也が初めて語る「心を動かす手紙の技術」! 手紙は、誰もが日常的に扱えるものです。でも、この力を本当に活用できている方は、ごく少数。本当なら、ふつうなら会えない人に会えたり、身近な人に心から喜んでもらえたり、といった、素晴らしい現実を導くツールなのです。本書は、水野敬也の経験にもとづいた実践的な手紙の力が身につき、さらに読後に静かな感動をおぼえる、新しい名著です。
ひとこと感想
水野さんの本はクスッと笑えたり泣けたりする本が多いですが、この本は「手紙」にフォーカスした本で、少々テクニック的な要素も盛り込まれている内容でした。しかしさすがの水野さん、その中にもユーモアもあり楽しく読めました。手紙の書き方や書く時の意識の持ち方、そこらへんが学べる一冊でもあります。
印象に残った部分
人は、ウソに対して非常に敏感です。そこで、「感謝・感動」を伝える時は次のことを守ってください。「本音であること」
※本書より引用
1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書/藤尾秀昭
第一弾。30万部突破のベストセラー。読者が選ぶビジネス書グランプリ総合グランプリ受賞作。仕事ができる人はここが違う―。人間力と仕事力が身につく。一流プロフェッショナル、365人が贈る仕事のバイブル。1日1話1頁、日めくり形式で読める全424頁のまさに永久保存版 。
ひとこと感想
1日1話、すごい人たちのお話を読んでいくスタイルです。心動かされる熱い話がたくさん出てきます。習慣づけの第一歩におすすめです。1日1ページ、いかがでしょういか。
印象に残った部分
「小さなことを重ねることがとんでもないところに行く唯一つの道」-byイチロー
※本書より引用
大谷翔平120の思考/大谷翔平
本書は、そんな大谷思考を彼自身の言葉で浮き彫りにした語録集である。大谷語録を読めば大谷の成功のベースとなった思考を知ることができる。同時に大谷思考を読み解けばそこには生きるためのヒントが散りばめられていることを感じとることができる。
ひとこと感想
大谷の考え方がびっしりと書かれた一冊です。WBCでも大活躍であった大谷選手ですが、野球に対する姿勢や考え方には本当に感心させられます。いい意味での「野球バカ」、そんな彼の人間性が良くわかる本でした。大谷がんばれ。
印象に残った部分
理不尽極まりない災難以外、自分の身の回りに起きることの大半は、自分の中に原因がある。向上心とは、己との対話を深めることなのかもしれない。
※本書より引用
人望が集まる人の考え方/レス・ギブリン
人生に成功と幸福をもたらすのは、人間関係を築く技術である。
本書では小手先のテクニックではなく、人間の本性に対する理解にもとづいた「基本原理」を紹介していく。
ひとこと感想
読んでいて刺さる場面が多々あった一冊でした。自尊心についてたびたび触れられており、そうだよなあと思いながら読み進めました。とても面白くておすすめの一冊です。
印象に残った部分
人々は自尊心を傷つけられると感情的になりやすいが、自尊心を大切にしてもらうと理性的に振る舞う。自尊心は人間の尊厳にかかわる大変重要なものだ。すべての人は自分の自尊心を大切にしてほしいと願い、それを傷つける人を敵とみなす。
※本書より引用
「やりたいことの見つけ方」がすごい!/リチャード・プロディ
著者がいちばん発見したかったのは、なぜ人生が「まあまあ満足」程度で推移し、時たま「穴」に落ち込むが、決して「素晴らしい」レベルに到達しないのか……であった。本書の中で、氏はその波乱万丈の旅の結果について語り、成功と幸福を得るためのガイドを提供している。ビル・ゲイツ氏も「驚くほど有益だ!」と絶賛した、米国発のロングベストセラー。
ひとこと感想
自己啓発本は何冊も読んできていますが、何冊読んでも本ごとにそれぞれ学べることがあるのが読書の面白いところであると改めて思いました。人生を自分の力で買え、楽しく生きていこう!そう思わせてくれる一冊です。とても面白かった。
印象に残った部分
「アドバイスをもらうのに好ましくない相手の方が、積極的に君にアドバイスをくれる」なんてことが、往々にしてある。だからこそ、誰かにアドバイスを求める時は、まず「誰の声に耳を傾けるべきか」をちゃんと見定めるところから始めなきゃいけない。
※本書より引用
賢者の睡眠/メンタリストDaiGo
本書では、DaoGoが最新のエビデンスから導き出した「爆眠」メソッドを紹介。遺伝子によって理想の睡眠&生活のタイミングが決まる、最新の「クロノタイプ診断」から、毎日の習慣として続けている「モーニングルーティーン」「ナイトルーティーン」も大公開! !朝起きた時に、睡眠の質を数値で確認してから、一日のタスクを決めるほど、「眠りの質」を行動の指針とするDaiGoが、人生における睡眠の重要性について語ります。
ひとこと感想
睡眠に関する様々な研究データが載っていて、知らなかった情報もいくつかあってとても勉強になりました。眠れないときに無理して眠らなくていい、寝ないようにしようとすると逆に寝れる、カフェインで眠れなくなる理由など、いろいろと知ることができて楽しかったです。
印象に残った部分
生きがいや目的があるから、人生に不安が少ない。だから寝つきもよくなり、しっかり眠れる。しっかり眠れるから、体も心も十分に休められる。十分に休息できるから、目覚めたらすぐに精力的に活動できる。体調もメンタルの状態も良好だから、集中力も行動力も上がる。日中、健全に活動できるから、夜、ぐっすり眠れる。
※本書より引用
あした死ぬかもよ?/ひすいこたろう
累計60万部突破名言セラピーシリーズのひすいこたろう最新刊!「いつ最後の日が来ても後悔はない」。そう胸をはって言える人生を送っていますか?人は、なぜかみな、「自分だけは死なない」と思っているものです。でも、残念ながら、みな、いつか必ず死にます。それを受け止めることこそ、「生」を輝かせることにつながります。自分が「いつか死ぬ身である」ということをしっかり心に刻み込めば、自分のほんとうの気持ちに気がつき、もっと自分らしく、人生を輝かせることができるのです。
ひとこと感想
タイトルにもあるように、いつ死ぬかわからないからこそできることとは何なのかを考えさせられる一冊でした。やりたいと思ったら行動に移そう。今、当たり前に会えている人、できていることに感謝をしよう。そう思わせてくれた一冊です。ありきたりですが、今を大切に生きよう。
印象に残った部分
鼻くそをほじっていたって、寿命は縮まっている。鼻くそをほじっていたって、それは命がけでやっているんです。だから、いま、あなたはこの本を命がけで読んでいる。現実を見よう。「メイント・モリ」。死を忘れるな。
※本書より引用
13階段/高野和明
犯行時刻の記憶を失った死刑囚。その冤罪を晴らすべく、刑務官・南郷は、前科を背負った青年・三上と共に調査を始める。だが手掛かりは、死刑囚の脳裏に甦った「階段」の記憶のみ。処刑までに残された時間はわずかしかない。2人は、無実の男の命を救うことができるのか。江戸川乱歩賞史上に燦然と輝く傑作長編。
ひとこと感想
久しぶりに小説を読んでみましたが、普段の読み方のななめ読みでは太刀打ちできず、じっくりと呼んで楽しめました。ミステリー小説の醍醐味でもあるラストでの目まぐるしい展開が見どころだと思います。また、死刑や冤罪についてがテーマの小説なのでそこに興味がある方にはとてもおすすめです。
印象に残った部分
いいか。こいつは二者択一なんだ。今、俺たちの目の前では、二人の人間が溺れてる。一方は冤罪の死刑囚、もう一方は強盗殺人犯だ。ひとりしか助けられないとしたら、どっちを助ける?
※本書より引用
喜ばれる人になりなさい/永松茂久
人生で大切なことは、母から繰り返し言われた「この一言」だった──3坪のたこ焼き屋から、口コミだけで県外から毎年1万人を集める大繁盛店を作り、2020年のビジネス書年間ランキングでも日本一に輝いた著者が贈る、母から学んだ、人生で大切な「たった1つ」の教え。学びあり、青春あり、涙あり、感動ありの成長物語。母と子、父と子、愛情、友情、師弟、家族、仕事の真髄が凝縮された、長編ノンフィクション。今の時代だからこそ読みたい、読むだけで自己肯定感が上がり、誰かのために何かをしたくなる、優しくて懐かしくて温かい一冊です。
ひとこと感想
「人は話し方が9割」の著者の実話が描かれた一冊。あの名著が出来上がる経緯を知ることができます。自分本位ではなく、相手に喜ばれる人になろうと思わせてくれる一冊です。身近な人へあらためて感謝できる一冊。
印象に残った部分
喜ばれるとは、自分の声を聴くということ。本来の愛に包まれた自分に気づくということ。自分の人生の指揮権を握るということ。自分の人生を生きるということ。
※本書より引用
天才IT大臣オードリー・タンが初めて明かす問題解決の4ステップと15キーワード/オードリー・タン
世界最高の頭脳による問題解決が、この一冊に。あらゆる難題を解決してきた台湾IT担当大臣オードリー・タンの思考法を大公開。最年少でデジタル政務委員に就任し、台湾の新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めた彼女は、世界をどのようにみているのだろうか。「すべての人の側に立つ」という信念、そして15のキーワードから、彼女と一緒に日常生活から社会問題までを考えよう。
ひとこと感想
著者独自の視点での考え方が書かれていて「なるほどこういう考え方があるのか」と思いながら読むことができました。少し難しいなと感じてしまう内容のところもありましたが、共感できたり学びになる内容もありました。読書レベルを上げていきたい。
印象に残った部分
オードリーは「AI時代が到来しても恐れる必要はない、ロボットはクリエイティブな仕事を担うことができないため、むしろ人が仕事を選べるようになる」と考えている。公共の価値と公共の利益の重視に基づき、彼女はCIをAIと結び付ければ、労働者はAIの力を借りて仕事の質を向上させることができると主張しているのだ。
※本書より引用
世界史を大きく動かした植物
一粒の小麦から文明が生まれ、茶の魔力がアヘン戦争を起こした――。人類は植物を栽培することによって農耕をはじめ、その技術は文明を生みだした。作物の栽培は、食糧と富を生み出し、やがては国を生み出した。人々は富を奪い合って争い合い、戦争の引き金にもなった。歴史は、人々の営みによって紡がれてきたが、その営みに植物は欠くことができない。人類の歴史の影には、常に植物の存在があったのだ
ひとこと感想
植物の話は知らないことばかりなのでこの本もやはり面白かったです。植物の歴史や植物の壮大な神秘的な魅力がとても伝わる一冊でした。各省ごとに一つの植物をテーマにいろいろな話が書かれていて楽しみながら読むことができます。おすすめです。
印象に残った部分
インドでは、カレーはとろみがなく、スープ状である。しかし、イギリス海軍では船の揺れに対応するために、カレーにとろみをつけるようになったと言われている。このとろみのあるカレーが、現在、私たち日本人が愛するカレーライスの原型なのである。
※本書より引用
僕が親ならこう育てるね/ひろゆき
ひろゆき的思考で語る初めての教育&子育て論!「勉強」「お金の使い方」「インターネットの使い方」について、子育て&教育において直面する悩み&問題について、どの本よりもわかりやすく「子育ての正解」をマジメに論じる!
ひとこと感想
ひろゆき視点での「子育て」についての考え方が詳しく書かれていて非常に面白かったです。日本の教育が間違っているというのはよく言われることですが、それをひろゆきの視点から「こうやったらいいんじゃない?」という提案ベースで書かれている点が「なるほどな」と思って読めました。面白かった。
印象に残った部分
料理で包丁や火を扱ったり、ストーブに石油を入れたりと、危険だから子供に真似してほしくないけどやらなきゃいけないこともあります。それは「見えないようにやる」のではなくて、むしろ「見えるようにやる」が正しいと思います。子供には「危険だ」ということを隠すのではなく、危険であることをきちんと教えた方がいいわけです。
※本書より引用
最高の体調/鈴木祐
本書では、より総合的なアプローチを取ります。
まずは現代人が抱える問題の「共通項」をあぶりだし、そのうえで、すべてを柔軟に解決する汎用的なフレームワークを提供するのが最終的なゴールです。
ひとこと感想
現代病や体調について書かれた内容になっていて、古代との環境の違いから生まれるストレスや不安が体調に影響を及ぼしているのだなと思いました。公園に出て自然に触れたり、遊びの意識をもって日々を過ごすことで健康的に暮らしたいなと思いました。
印象に残った部分
スマホは現代人の生活を大きく変えましたが、その一方で古代に生まれた脳は技術の発達に追いつけず、限りある認知のリソースをムダに消費しています。その点で、現代人の集中力の低下も立派な文明病の一つなのです。
※本書より引用
面白くて眠れなくなる植物学/稲垣栄洋
本書は、ロングセラー『身近な雑草の愉快な生きかた』の著者による、読みだしたらとまらない、すごい植物のはなし。植物は当たり前のように私たちの身の周りにありますが、けっして何気なく生えているわけではありません。植物の生態は、私たちが思っているよりもはるかに不思議であり、謎に満ちています。本書は、そんな植物の魅力を解き明かす一冊です。
ひとこと感想
タイトルの通り本当に面白くて眠れなくなるほどの内容でした。知的好奇心を大きくくすぐられます。「植物学」というこれ前にあまり学んでこなかったジャンルだからこその新しい学びがたくさんあって本当に面白かったです。植物の神秘的な力や生命力のすごさ、不思議に迫った内容の一冊。おすすめです。
印象に残った部分
すべての生物は、自分の徳だけのために行動しています。しかし、そんな利己的な行動が、人間から見るといかにも助け合っているかのような、お互いに特になる関係が作られているのです。自然界の仕組みというのは、本当によくできています。
※本書より引用
人工知能は人間を超えるか/松尾豊
グーグルやフェイスブックが開発にしのぎを削る人工知能。日本トップクラスの研究者の一人である著者が、最新技術「ディープラーニング」とこれまでの知的格闘を解きほぐし、知能とは何か、人間とは何かを問い直す。
ひとこと感想
人工知能の未来世について専門家である著者が書いた一冊で非常に興味の湧く内容でした。人工知能は期待されているほどの破壊力は恐怖は現時点ではないですが、それでも人類史を大きく変える力を持っていることも事実だということを知り、未来がより楽しみになりました。これからの人工知能界に期待です。シンギュラリティはなかなか起きることではないとのこと。安心安心。
印象に残った部分
人工知能について報道されているニュースや出来事の中には、「本当にすごいこと」と「実はそんなにすごくないこと」が混ざっている。「すでに実現したこと」と「もうすぐ実現しそうなこと」と「実現しそうもないこと(夢物語)」もごっちゃになっている。それが混乱のもとなのだ。
※本書より引用
朝1分間、30の習慣。/マツダミヒロ
1日のスタートである「朝」という時間をどのように過ごすかで、その日が素敵な1日になるか、残念な1日になるかが決まります。人生とは、今日1日の積み重ね。つまり、朝との向き合い方で幸福度は変わるのです。
ひとこと感想
習慣に関する本はたくさんありますが、本書は「毎日無理してやる必要はない」「1分だけでいい」などと、とにかくハードルが低く設定されていて、習慣化するには理にかなっている内容だなと思いました。朝起きて「今日、どんな1日にしたい?」その問いかけから始めていきたいです。
印象に残った部分
「空っぽの状態に好きなものを取り入れること」これが、最大のしあわせを感じるコツです。そして、1日の中で、この空っぽの状態こそが「朝」なのです。自分が好きなこと、しあわせを感じることは、1日の中の早い時間帯に行いましょう。それが自分で自分の期限を良くさせ、その後のモチベーションアップに直結します。
※本書より引用
すぐやる人は、うまくいく/中谷彰宏
「すぐやる人」は、仕事でも、恋愛でも、チャンスをつかむ。すぐやるコツを紹介する。【この本は、3人のために書きました。】(1)なかなか始めることができない人。(2)チャンスを速くつかいみたい人。(3)部下の仕事を、スピードアップさせたい人。
ひとこと感想
タイトルの通り、すぐやる人はうまくいくという内容が様々な角度から描かれていて、「そりゃそうだよな」「すぐに行動に移そう」と思わせてくれる一冊でした。1時間もかからずにサクッと読めてしまうのでとてもおすすめです。ビジネスマン必読の一冊だと思います。
印象に残った部分
瞬間で出た答えが、正解。考えて、間違う。決断するときは、答えは2秒で出ます。これは脳科学でも証明されています。2秒考えても、2時間考えても、答えの精度は同じです。雑音が入ってくる前に決断するのが、一番正しいのです。
※本書より引用
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。
気になった本がありましたら是非読んでもらえたらなと思います。おすすめの本もたくさんあります。
2023年読んだ本、現在34冊。
意気揚々と立ち上げが記事ですが、2023年は34冊で幕を閉じました。来年もよろしくです。
読書は楽しいぞ。
ではまた。
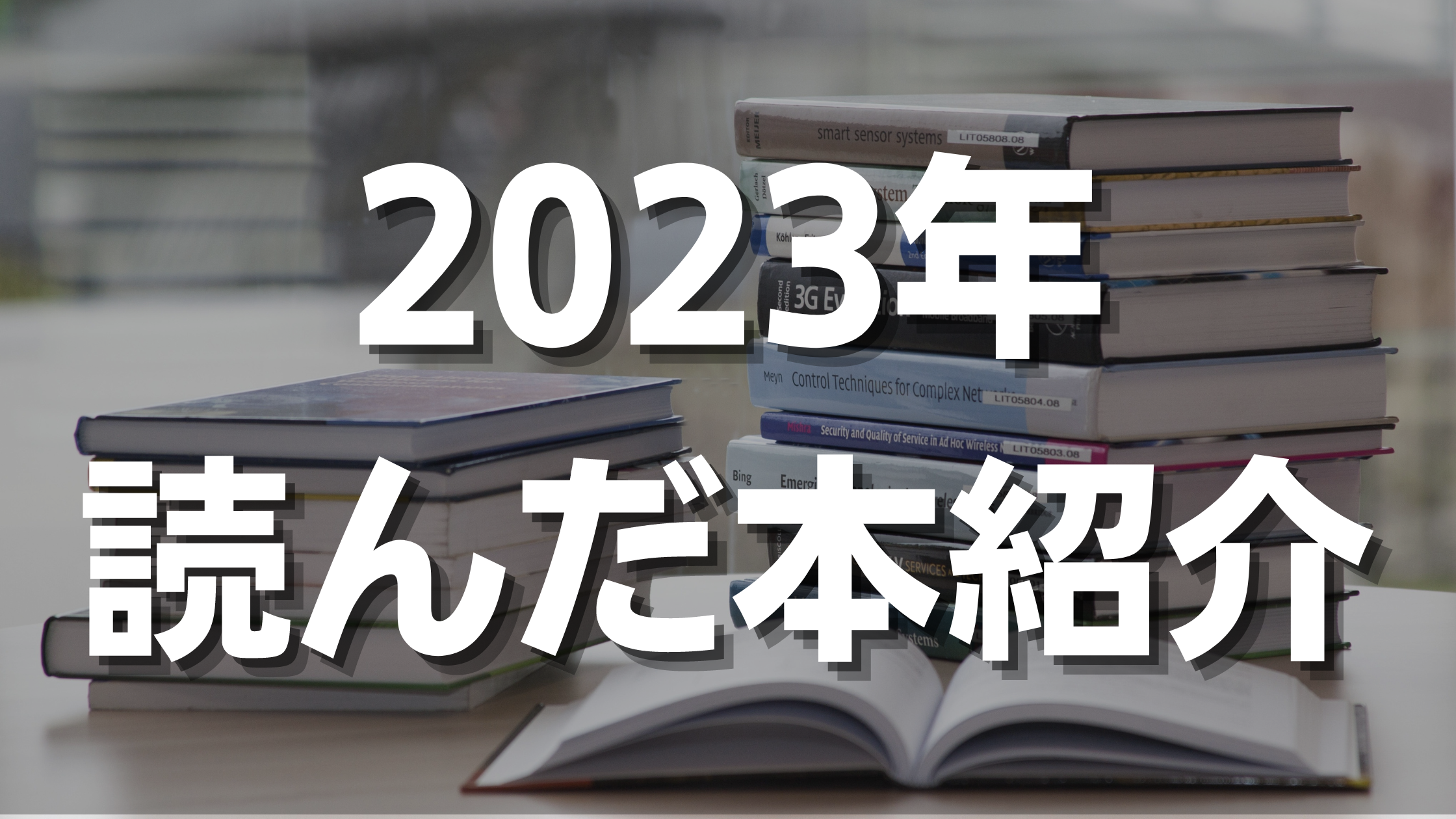
















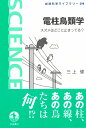




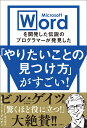


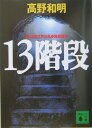


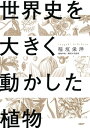






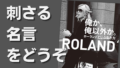
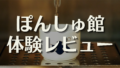
コメント